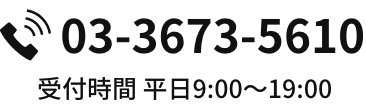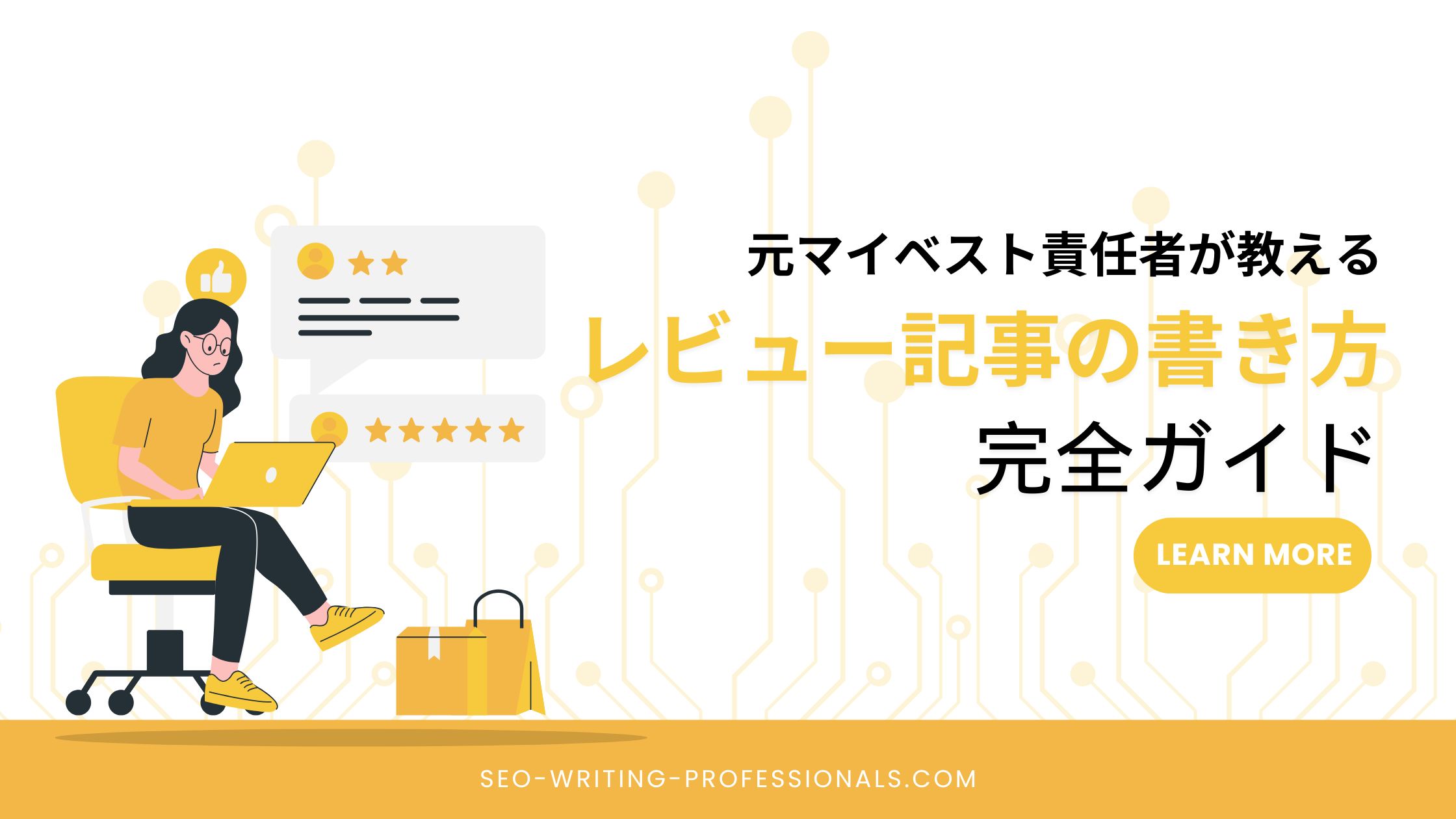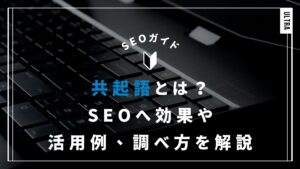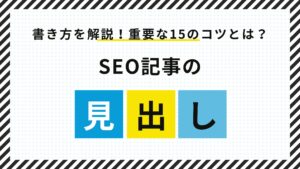- 元マイベスト責任者が教える商品レビュー記事の書き方
- 初心者でも使える構成やコツ

この記事の著者:伊藤 寛規
月間5,000万PV越えのWebメディア「mybest」でコンテンツ制作責任者を経験。「転職サイト」「マッチングアプリ」「退職代行」「動画配信 おすすめ」「クレジットカード」など、日本最難関クラスのキーワードで検索上位獲得した実績多数あり。
メディアの新たな収益源として、商品レビュー記事(以降、レビュー記事)の作成を考えていても「具体的に何を書いたらいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
レビュー記事は収益化に適しているコンテンツとして、多くのメディアやブログが作成しています。しかし、「売れるレビュー記事」を作成するにはコツが必要です。
そこで本記事では、読者が買いたくなるようなレビュー記事の書き方について詳しく解説します。
初心者でも使えるレビュー記事の構成テンプレートも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
▼伊藤への記事制作のご依頼は下記より承っております。
(「伊藤希望」の旨を担当者にお伝えください。)
- SEOで高い成果が出せる外注先に記事制作を依頼したい
- クラウドソーシングは管理が大変で品質もムラがある
- SEO特化型の記事作成代行業者は高いし最低記事数の縛りがある

現在、上記のようなお困りごとがありましたらぜひとも私たち記事作成代行ウルトラへご相談ください。納品した記事の約40%が検索1位を獲得している業界屈指のSEOチームが成果に直結する記事を業界最安級の文字単価4.5円~提供します。さらに最低記事数や契約期間の縛りなく1記事からご依頼いただけます。
レビュー記事が収益化に適している理由
レビュー記事が収益化に適している理由は、商品の購買意欲が高いユーザーにアプローチできるからです。
過去に総務省が行った調査によると20代~40代の約80%が商品レビューを参考に、商品を買っていることがわかっています。
実際に、ネットで商品を購入する際、「〇〇 口コミ」や「〇〇 評判」といったキーワードで検索した経験はありませんか?
商品の購入を迷っているユーザーは、購入前に使用感などのレビューを確認することで、最終的に購入するかどうかの判断をしています。
そして、レビュー記事を見ているということは、ユーザーはその商品に興味を持っている状態です。
レビュー記事でうまく背中を押してあげれば、購買につながる可能性が高いでしょう。
レビュー記事の書き方・構成
レビュー記事を作成する流れは、以下の通りです。
- レビュー記事を作成する商品を決める
- 商品・サービスをリサーチする
- 実際に商品・サービスを利用する
- 口コミを収集する
- レビュー記事の構成案を作成する
- 構成を修正しながら記事を執筆する
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
 伊藤
伊藤ここで紹介する作成の流れは、あくまでも一例です。順番や内容は自社に合った形に変更しながら活用してください!
1. レビュー記事を作成する商品を決める
まずは、レビュー記事を作成する商品・サービスを決めましょう。
商品・サービスを選ぶ際は、以下のような基準を参考に考えてみてください。
- アフィリエイト単価が高い商品・サービス
- 業界で注目されている最新商品・サービス
- 季節やトレンドに沿った商品・サービス
- 商品名での検索ボリュームが多い商品
例えば、レビュー記事を作成することで売上アップを目指したいのであれば、アフィリエイト単価が高い商品や、季節・トレンドに沿った商品を選ぶのがおすすめです。
また、自社が打ち出したい商品やサービスがあれば、レビュー記事を作成することで商品への訴求力を高められるでしょう。
 伊藤
伊藤特に、「クレジットカード」や「転職エージェント」などの無形商材は、サービスによって大きくアフィリエイト単価が異なるので、作成する優先度に注意しましょう。
2. 商品・サービスをリサーチする
次に、レビュー記事を作成する商品・サービスについて、リサーチをしましょう。
具体的には、以下のようなことを調査し、商品の基本的な情報や利用者の傾向などを把握することが大切です。
- 商品のスペック
- 価格
- 商品の特徴やメリット・デメリット
- どんなユーザーをターゲットにした商品か
- どこで買えるか
なお、商品についてリサーチする際は、必ずメーカーの公式サイトや信頼に足るメディアを参考にしてください。
誤った情報をもとにレビュー記事を作成してしまうと、商品やサービスの提供元からのクレームにつながるおそれもあります。
3. 実際に商品・サービスを利用する
商品やサービスについてある程度理解できたら、実際に商品・サービスを購入して使ってみましょう。
リサーチで把握した特徴やメリット・デメリットが本当かどうかや、ターゲットとしているユーザーにとって良い商品かどうかなど、消費者目線で商品を確認し、感じたことをメモに記録しておくとよいでしょう。
また、パソコンのキーボードのように、使用感を把握するのに時間がかかる商品の場合は、長期間使用してからレビュー記事を作成するのがおすすめです。
実態に即した使い方をしたうえで「〇ヵ月使ってみた感想をレビュー!」のようなレビュー記事を作成することで、よりユーザーの役に立つコンテンツに仕上がるでしょう。
 伊藤
伊藤レビュー記事において最も大切なのは「実際に商品やサービスを使ったことが書いている」ことです。商品やサービスを使ったこともない人が記事を書いていても、説得力はありません。費用はかかりますが、記事を作る前に必ず商品やサービスを使ってみましょう。
4. 口コミを収集する
次に、実際にその商品を使ったことがある人の口コミを集めましょう。
商品の使用感は、レビュー記事を作成する人の感想だけでは足りません。人によって感じ方は違うので、何人かの口コミを収集するのがおすすめです。
なお、口コミを集めるには以下のような方法があります。
- 社内でほかの社員に商品を使ってもらい、口コミを集める
- クラウドソーシングサービスで口コミを集める
- ほかのメディアやSNSの口コミを引用する
最もおすすめなのは、社内でほかの社員に商品を使ってもらって口コミを集める方法です。
どんな観点に着目して商品を使ってほしいかや、必要なレビュー項目も伝えられるので、記事に役立つ口コミを集めやすいでしょう。
一方、クラウドソーシングでの口コミ収集は手軽な反面、「本当にその商品を使ったことがある人の口コミか」がわからない点に要注意です。
クラウドソーシングはお小遣い稼ぎ目的で登録している人も多く、口コミを集めても当たり障りのない内容しか収集できないケースもあります。
できるだけリアルな口コミを集めるには、やはり自社の社員や知り合いに実際に商品を使ってもらうのがよいでしょう。
 伊藤
伊藤どうしても商品を用意するのが難しい場合は、ほかのメディアやSNSからの口コミの引用も検討しましょう。
5. レビュー記事の構成案を作成する
次に、レビュー記事の構成を作成します。
レビュー記事の構成案には、以下のような内容を盛り込むとよいでしょう。
| レビュー記事の構成案例 |
|---|
| リード文:読者への共感やこの記事でわかること h2:商品の基本情報 h2:商品の特徴 ┗h3:特徴① ┗h3:特徴② h2:商品のメリット ┗h3:メリット① ┗h3:メリット② h2:商品のデメリット ┗h3:デメリット① ┗h3:デメリット② h2:商品を使ってみた感想 ┗h3:感想① ┗h3:感想② ┗h3:感想③ h2:商品を使った人の口コミ ┗h3:口コミ① ┗h3:口コミ② ┗h3:口コミ③ h2:その商品がどんな人におすすめか ┗h3:商品がおすすめな人① ┗h3:商品がおすすめな人② ┗h3:商品がおすすめな人③ h2:まとめ |
構成案を作成する際は、記事のターゲットやペルソナの設計も忘れずに行ってください。
商品やサービスをどんな人に売り出したいのか、どんな人に買ってほしいのかを明確にすることで、より訴求力が高いレビュー記事を作成できるはずです。
 伊藤
伊藤レビュー記事の構成はテンプレート化して、ほかの商品のレビュー記事でも使えるようにするのがおすすめです。構成をテンプレート化できれば、効率的にレビュー記事の作成を進められるでしょう。
6. 構成を修正しながら記事を執筆する
レビュー記事の構成ができたら、実際に記事を執筆しましょう。
商品に関する基本的な情報はもちろん、実際に使ったからこそわかる内容を盛り込んでください。
また、執筆する際は、必要に応じて構成を修正することも大切です。メリットやデメリット、どんな人におすすめかなどがより伝わりやすい内容になるように心がけましょう。
なお、執筆の際はSEOライティングを徹底することも大切です。「SEOライティングとは?プロが実践する39のコツ<初心者必見>」を参考に、キーワードを意識した文章を作成しましょう。
売れるレビュー記事を書くための6つのコツ
ここからは「売れるレビュー記事」を書くためのポイントとして、以下6つを紹介します。
- ユーザーの悩みを解決できるメリットを提示する
- ユーザーに利用シーンを想起させる文章を作成する
- 記事内ではリアルな写真を使う
- 「限定感」や「今買うべき理由」を意識する
- メリット・デメリットを両方紹介する
- 別商品との比較パートを設ける
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
ユーザーの悩みを解決できるメリットを提示する
商品のメリットを解説するときは、ユーザーの悩みを解決できる具体的なメリットを提示することが大切です。
例えば、カメラの「手ぶれ補正」をメリットとして挙げる際の訴求方法を見てみましょう。
| 良い例 | 手ぶれ補正があることで、子どもの運動会や試合でもきれいな写真を残せる。 |
|---|---|
| 悪い例 | 手ぶれ補正があるので、動いている被写体の撮影に向いている。 |
2つの例のうち、上の例のほうがより具体的なメリットを提示できており、ユーザーが実際に自分の悩みを解決できるイメージが湧くはずです。
もちろんこれは一例で、同じ「手ぶれ補正」というメリットであっても、ターゲットやペルソナによって、訴求方法は大きく異なります。
このように、レビュー記事でメリットを紹介する際はユーザーの悩みに沿ってより具体的なメリットを提示することを心がけましょう。
 伊藤
伊藤自分がターゲットやペルソナになった気持ちでメリットを考えるのがポイントです!
ユーザーに利用シーンを想起させる文章を作成する
商品の特徴やメリットを紹介する際は、ユーザーにその商品を使うシーンを想起させることを意識しましょう。
例えば、先ほどの「手ぶれ補正」のメリットについて紹介する際、文章により具体的な利用シーンを盛り込むと以下のようになります。
| 良い例 | 手ぶれ補正があることで、子どもの運動会でもきれいな写真を残せます。子どもの雄姿をしっかり写真に残せれば、あとで家族みんなで見返して楽しむこともできますよ。また、手ぶれ補正があれば三脚を使う必要もないので、運動会当日の余計な荷物を減らせるでしょう。 |
|---|---|
| 悪い例 | 手ぶれ補正があることで、子どもの運動会でもきれいな写真を残すことができます。 |
少し極端な例ですが、「家族みんなで写真を見返せる」や「運動会当日の荷物が減る」といった具体的な利用シーンを盛り込むことで、「手ぶれ補正」というメリットの訴求力が上がっているはずです。
 伊藤
伊藤極論ですが「手ぶれ補正」というメリット自体は、メーカーの公式サイトを読めばわかることです。レビュー記事の独自性を高めるためにも、具体的な利用シーンを盛り込むことを意識しましょう!
記事内ではリアルな写真を使う
レビュー記事の中では、できるだけリアルな写真を使いましょう。
例えば、公式サイトから引用した画像を使うよりも、実際に商品を触っているところを撮影した写真などを使用するのが理想的です。
ユーザーは「実際に商品を使ったことがある人」のレビューだからこそ価値を感じるので、あえて素人感のある写真を使うのもよいでしょう。
例えば、以下のカメラのレビュー記事では、実際に使っているカメラの写真が記事内で使用されています。

リアルな写真を使うことで、ユーザーへの訴求力が高まるのはもちろん、コンテンツの独自性もアップするので、社内での撮影を積極的に行うとよいでしょう。
 伊藤
伊藤もちろん、公式画像の引用が悪いというわけではありません。自前の写真は良くも悪くも素人感が出るので、メディアの運営方針に合わせて使う写真を選んでくださいね。
「限定感」や「今買うべき理由」を意識する
レビュー記事から商品の購買を促すためには「限定感」や「今買うべき理由」を意識することも大切です。
例えば、文章や見出しに以下のような言葉を盛り込むことで、ユーザーの購買を後押しできるでしょう。
- 今だけ!〇〇まで限定!
- 期間限定のキャンペーンあり
- 買うなら今が一番お得
特に、アフィリエイト案件がある商品の場合、限定のキャンペーンを実施しているケースも多いので、積極的に活用してください。
メリット・デメリットを両方紹介する
レビュー記事では、メリット・デメリットの両方を紹介することが大切です。
メリットしか紹介されていない記事はユーザーに不信感を与えてしまい、購買につながらない可能性があります。
どんな商品にも必ずメリット・デメリットが存在するはずなので、デメリットと感じたことも隠すことなく紹介しましょう。
とはいえ、デメリットを無理に押し出す必要はありません。「〇〇な人にはおすすめだけど、〇〇な人には不向き」のように、柔らかい表現で紹介することも検討してください。
 伊藤
伊藤2023年にGoogleが行ったプロダクトレビューアップデートでは、SEOにおいてもメリット・デメリットの両方を紹介することが推奨されています!
別商品との比較パートを設ける
レビュー記事では、紹介する商品と似た商品との比較パートを設けるのもおすすめです。
ユーザーの中には、ほかの商品との比較をせずにその商品を調べている人もいます。
仮に、レビュー記事で紹介した商品がユーザーのニーズに合っていなかった場合、ほかの選択肢がないとそのまま離脱されてしまうでしょう。
その点、類似商品や紹介した商品のデメリットをカバーできる商品を一緒に紹介することで、別の商品の購買へつなげられる可能性があります。
「この商品が気になる人におすすめのアイテム」や「こちらの商品もおすすめ!」など、類似商品を紹介するパートも積極的に活用してみましょう。
 伊藤
伊藤レビュー記事で紹介した商品をランキング記事でも紹介している場合は、ランキング記事へのリンクも設置するのがおすすめです!
レビュー記事のSEOで勝つためのポイント
ここまで、レビューの書き方やコツを解説してきました。しかし、せっかく作成したレビュー記事も、SEOで上位に表示できなければ成果につなげることはできません。
そこでここからは、レビュー記事のSEOで勝つためのポイントとして、以下4つを紹介します。
- 上位獲得を狙うキーワードを明確にする
- レビュー記事でもE-E-A-Tを意識する
- 商品の情報は定期的に更新する
- 関連ページと内部リンクとつなぐ
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
上位獲得を狙うキーワードを明確にする
レビュー記事を作成する際は、SEOで上位獲得を狙うキーワードを明確にしましょう。
具体的に、レビュー記事で狙うべきキーワードには以下のようなものがあります。
- 「商品名+口コミ」
- 「商品名+ 評判」
- 「商品名+レビュー」
- 「商品名+使ってみた」
ただし、どのキーワードについてメインで対策すべきかは商品によって異なります。検索ボリュームを調べるほか、競合サイトを分析してキーワードを選びましょう。
また、商品によっては英語表記か日本語表記かによっても検索ボリュームが異なる場合があるので、注意してください。
なお、キーワードの選定方法については「SEOキーワード選定完全ガイド|実行手順や注意点・活用ツールまで」でも詳しく解説しているので、あわせてチェックしておきましょう。
レビュー記事でもE-E-A-Tを意識する
レビュー記事のSEOで検索上位を獲得するためには、E-E-A-Tを意識しましょう。
E-E-A-Tとは、以下4つの単語の頭文字をとった言葉で、Googleがサイトやコンテンツを評価する際に重視している指標です。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
レビュー記事では「実際に商品を使ったことがある人」が記事を書いていることのほか、その商品に精通している人が執筆・監修していることが重要です。
特に、カメラやパソコンなどレビューにある程度の専門知識が必要な場合は、専門家に協力してもらうとよいでしょう。
また、記事の冒頭や末尾に監修者や執筆者の情報を記載することも忘れてはいけません。
なお、記事監修については「記事監修とは?SEOへの影響や依頼の流れ・監修者の選び方まで徹底解説」でも詳しく解説しています。監修者情報の記載方法や監修者の選び方がわからない方は、ぜひ参考にしてください。
また、SEOにおける著者(=執筆者)情報の重要性については、「SEOで著者情報は重要!理由や最適化方法、構造化データまで解説」を参考にしてください。
商品の情報は定期的に更新する
一度作成したレビュー記事は、定期的に商品やサービスの情報を見直して更新するようにしましょう。
SEOにおいては、記事内の情報が最新であることも重視されています。
商品に関する情報が変わっていない場合、無理に記事を更新する必要はありませんが、商品の内容が変更された場合は、記事の内容も速やかに修正しましょう。
特に、サブスクリプションやアプリなどの無形商材については、アップデートなどで商品情報が更新されることが多いので、注意してください。
 伊藤
伊藤すべての記事を定期的に更新するのが難しい場合は「いつ作成した記事なのか」がわかるように記事内に明記してください。また、すでにSEOで検索上位を獲得できている記事や注力したい記事については、優先的に更新するのがおすすめです。
関連ページと内部リンクとつなぐ
レビュー記事のSEOで検索上位を獲得するには、関連ページとの内部リンク構造の構築も忘れてはいけません。
内部リンクをつなぐことで、Googleからその商品に関する専門性が評価され、SEOにポジティブな影響を与える可能性があります。
例えば、レビュー記事で紹介した商品・サービスが含まれるランキング記事や、同じメーカーの類似商品のレビュー記事などへリンクを設置するとよいでしょう。
このように、関連ページの内部リンクをつなぐSEO対策のことを「トピッククラスターモデル」と呼びます。
ただし、内部リンクはただ設置すれば良いわけではありません。リンク設置にはいくつかのポイントがあるので「トピッククラスターモデルとは?SEO効果や作り方、事例まで」を参考にしてください。
レビュー記事を書く際の注意点
最後にレビュー記事を作成する際の注意点として、以下4つのポイントを紹介します。
- 広告記事の場合はPR表記が必要
- 誇張しすぎた表現は避ける
- 専門用語を使いすぎない
- セールス感を出しすぎない
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
広告記事の場合はPR表記が必要
レビュー記事の作成について企業から広告料をもらっていたり、レビュー記事からの購買について広告主からの報酬が発生したりする場合、記事内にPR表記が必要です。
2023年に施行された景品表示法では、ステルスマーケティングに関する規制が強化され、アフィリエイトなどで報酬を得る場合であってもPR表記が必要とされています。
「あくまでもレビューだから広告にはならないのでは?」と思うかもしれませんが、レビュー記事で商品の購入を促し、報酬が発生している時点で規制となる可能性があるのです。
なお、ステマ規制についてはさまざまな法的解釈があるため、必ずしも「レビュー記事=広告」と判断されるわけではありません。
しかし、広告によって報酬が発生している場合はPRであることを明記しておくのが安心です。
誇張しすぎた表現は避ける
商品の購入を促すために、誇張した表現を使うのは避けましょう。メリットや商品の特徴を誇張して紹介すると、景品表示法に抵触する可能性があります。
特に、以下のような表現は避けるようにしてください。
- 科学的な根拠がないのに「絶対に痩せる」などの表現を使う
- 「定価10万円が今なら1,000円!」のように、実際より高額な定価を見せて、割引されているように見せる
また、景品表示法に違反していなかったとしても、メリットを誇張して伝えるとユーザーに不信感を与えてしまいます。「絶対」や「間違いない」などメリットを断定する表現には注意しましょう。
 伊藤
伊藤近年、ユーザーはステマや過剰なセールスに敏感なっています。商品を買ってもらうために過剰にセールス感を出してしまうと、逆効果のおそれもあるので注意しましょう。
専門用語を使いすぎない
レビュー記事の中ではできるだけ専門用語は使わず、だれが読んでもわかりやすい文章を心がけましょう。
どうしても専門用語を使って解説しなければならない場合は、事前に用語について解説するなどで工夫してください。
 伊藤
伊藤専門用語を使うべきかどうかは、記事のターゲットによっても異なります。玄人向けの商品やメディアの場合は、専門用語を使ったほうが魅力やメリットが伝わりやすいケースもあるので、メディアの運営方針に合わせた言葉遣いを意識してください。
まとめ
本記事では、商品レビュー記事について基本的な書き方や商品を売るためのコツ、注意点などを解説しました。
レビュー記事は収益化に適している反面、作成するにはさまざまなノウハウが必要なほか、予算やリソースも欠かせません。
自社でレビュー記事を作成する余裕がない場合は、記事作成代行サービスの利用も検討してください。
記事作成代行ウルトラには、当記事を執筆した私「伊藤」をはじめ、レビュー記事の作成に詳しいライター・ディレクターが在籍しています。
これまで2,000記事以上を作成してきた実績から、質の高いレビュー記事を作成し、売上アップやSEO改善をサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- SEOで高い成果が出せる外注先に記事制作を依頼したい
- クラウドソーシングは管理が大変で品質もムラがある
- SEO特化型の記事作成代行業者は高いし最低記事数の縛りがある

現在、上記のようなお困りごとがありましたらぜひとも私たち記事作成代行ウルトラへご相談ください。納品した記事の約40%が検索1位を獲得している業界屈指のSEOチームが成果に直結する記事を業界最安級の文字単価4.5円~提供します。さらに最低記事数や契約期間の縛りなく1記事からご依頼いただけます。